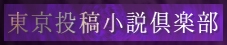面疔の悲劇
貴方は、 番目の読者です。
番目の読者です。
それは、日曜日の晩のことだった。
お風呂から上がると、バスタオルで顔を拭き、そのまま洗面台の鏡を覗き込む。
ガラスが半分曇っていたので、私は鏡に映る自分に接吻しそうなほど近付く。
「よし」
呟いて鏡から離れると、私はバスタオルで体を拭いた。
部屋に戻ると、机の上に辞書を重ね、さらにその上に鏡を置く。即席の手術台の
出来上がりである。
さらに、テッシュとマキロンを用意する。
おもむろに座り直し、鏡の中の半年間私を悩ませ続けた敵の姿を睨み付けた。
「覚悟なさい」
それは口には出さなかったが、まさに死刑宣告である。
敵の名は黒面皰。別名を、面疔という。
鼻をつまみ、面皰の芯を絞り出そうと試みる。しかし、半年間居座った私の鼻の
居心地がよほどいいのか、芯は容易には姿を現さない。そのくらいは覚悟の上であ
る。何しろ、この黒面皰との付き合いは半年間なのだ。お互いのことを知り尽くし
ていると言ってもいいだろう。鼻にある他の毛穴から油が吹き出てきたのをテッシ
ュで拭き、さらに鏡を睨む。強くつまんでいたせいで、鼻は真っ赤である。しかし
、ここで諦めては面皰に負けることになる。
鼻で溜息を吐き、座り直す。そして、息を深く吸って、止めて、再度チャレンジ
だ。指先に渾身の力を込め、黒い蓋のある毛穴に集中攻撃を掛ける。蓋は、僅かに
上昇した。指先に力を込め続ける。しかし、もう一息というところで息苦しくなる
。
鼻をつまんでいても口で呼吸したらいいと思われるかもしれないが、人間、何か
しら集中しているときには息を止めなければならないものである。
再びテカる鼻をテッシュで拭く。
そして、三度チャレンジである。
力を込めるに従って、ググッ、と敵は姿を現す。観念したか、ざまあみろ。そん
なことを思った瞬間、自らの脂汗で指が滑ってしまう。
いけない、いけない。焦りは禁物である。
丹念に鼻と指先の汗を拭き取り、敵の様子を窺う。幸いにも、こちらが力を抜い
た途端に再び穴に潜るという最悪の事態は回避されたようである。一人頷いて、私
はまた攻撃を掛ける。
指先の力を込める方向が一ミリでも狂えば、指はまた鼻の上を滑ってしまう。慎
重に、鼻をつまみ続ける。
「・・・!」
敵は、再三に渡るこちらの攻撃に対して、とうとう白旗を掲げて投降してきた。
やっと、敵の全貌が明らかになったのである。
私は、負けを認めた敵将には寛大な人間である。指先に敵を乗せ、しげしげと観
察する。虫眼鏡でも用意したいところである。
私と半年間に渡る攻防を繰り返した敵将は、まさに「敵ながら天晴れ」というも
ので、その姿はさながら「一回り小さい白胡麻」である。それでいて先端の部分が
黒ずんでいるのは、彼が黒面皰たる所以であろう。それにしても、こんな幅一ミリ
、長さ二ミリほどのものが、よくぞ自分の鼻に埋もれていたものだと思う。穴が空
いているのではないかと、不意に心配になって鏡を覗き込む。鼻には穴が空いてい
た。しかし、思ったほど大きくはない。今は、私の鼻には黒面皰の代わりに、ポチ
ッと赤い血が顔を覗かせていた。これこそ、「肉を斬らせて骨を断つ」である。こ
のくらいのリスクを覚悟していた私は、指の上の敵将を優しくティッシュに乗せる
と、別のテッシュをマキロンに浸して、戦場となった鼻を消毒する。いくら拭って
も血が出てくるが、これは仕方のないことである。
しかし、血を拭き取り、次の血が出てくるその一瞬の間に、私は見てしまった。
諦めの悪い残存兵か、伏兵か。どちらにしても、敵は全滅していなかったのである
。私は、テッシュの上で、今や私に生死を預けた敵将の姿を眺めた。この見事な敵
将に限って、伏兵を潜ませていたとは考えにくい。おそらく、諦めの悪い残存兵の
方であろう。ならば、根絶やしにするまでだ。
私は、汗と血で滑る鼻を、またつまんだ。
ぎゅっ、と力を込めると、敵は姿を現した。しかしそれは、敵ながら情けない姿
である。髪の毛よりもまだ細く、そして長さは六ミリほどもある白い物体が、私の
鼻から姿を現したのだ。それはまるで、「ジャックと豆の木」の豆の木がニョキニ
ョキと生えていく様子を連想させた。鼻を拭き、つまむと敵はまだ現れる。
「こりゃあ、予想に反して長期戦だな」
鼻を拭き、つまみ、拭き、つまみ・・・。それは、息の詰まる攻防であった。
しかし、指揮官のいない軍隊は、所詮まとまりがない。敵は全員私の前に姿を現
し、晴れて私は「官軍の将」となったのである。
「ふう・・・」
深呼吸をして、落ち着いて鏡の中の戦場を眺める。
そして、私は知ってしまったのだ。
敵は、私の鼻で地雷を爆発させていたのだということに。
私が鼻をつまむのに集中するあまり、敵の罠にはまって爪を立ててしまったのだ
。同じ場所を何度も爪を立ててこすったせいで、鼻の一番高い場所に横幅二センチ
縦幅一センチの水膨れが発生していたのである。
「・・・」
私は、テッシュの上の敵将を一瞥すると、鼻の上の水膨れを潰した。
そして、敵もろともテッシュを丸めると、ゴミ箱に投げ捨てた。
完全勝利である。作戦は完璧に遂行された。
一夜明けて、私の生活には先日の戦いなどなかったかのような日常が戻ってくる
。目覚まし時計に起こされて、眠い目をこすって顔を洗う。そしてタオルで顔を拭
いて、何気なく鏡を見る。
「!!!!!」
なんと、あろうことか鼻の一番高いところが、真っ赤になっている。これでは季
節外れな「真っ赤なお鼻のトナカイさん」である。
「・・・」
頭に浮かぶのは、「敵もさるものひっかくもの」という意味不明な言葉であった
。今やゴミ箱に露と消えた敵将は、しっかりと戦場に置き土産をしていったのだ。
彼に言わせれば、「死に花を咲かせた」のかもしれない。そう、「死に花」は私の
鼻に真っ赤に咲いていた。
それから一週間、私の鼻には彼岸花が咲き誇っていた。
今もなお、大きな毛穴として彼の墓標は私の鼻に深く刻み込まれている。
この作品への感想は、霜月萬季氏まで、メールでお願いします。
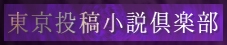
戻る